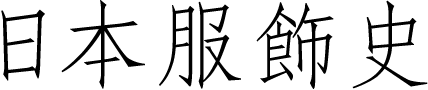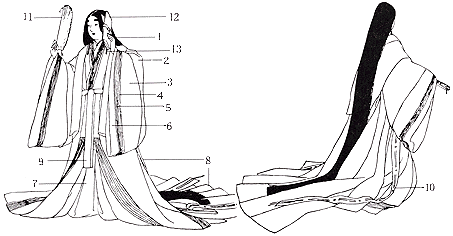男子の束帯にあたる成年婦人の朝服で、宮中の正装である。唐衣裳姿ともいわれ、今日俗に十二単と呼ばれている。このような姿は平安時代中期、十世紀後半には成立したと考えられる。これは中後期、十一・二世紀頃を想定し、禁色を許された高位の上臈の姿とした。この形式は多少形状の変化はあるが、長く伝統を持ち続け、今日も宮中の特殊儀式の服装として用いられている。
髪は垂髪(特別の儀式の時は、頭頂に結いあげ髻をつくり、これに平額、櫛、笄、釵子等を飾る)、眉は作眉とした。
衣服の構成は唐衣、裳(裳の着装は、唐衣より先につける場合と、後につける場合とがある)、その下に表着、打衣、袿、単、紅の袴、衵扇、帖紙、足には襪をはく。
初期は唐風文化の影響が
日本の古代史のなかで平安時代というのは延暦十三年(794)、平安京即ち現在の京都に都を遷された時から、建久三年(1192)、源氏の政権が確 立した頃、或いはそれ以前の文治元年(1185)、平氏の滅亡によって鎌倉の源頼朝の事実上の覇権が成立する頃迄の約四百年を云っているが、文化や服装の 面で云えば、その当初はむしろ、奈良時代そのままの唐文化の時代であった。平安時代を区分すると、律令政治の時代、藤原氏による摂関政治の時代の時代、院 政の時代、平氏政権の時代になる。
律令政治の時代といわれる初期は、嵯峨天皇の弘仁九年(818)の勅にあるように、天下の儀式、男女の衣服皆唐法に依る時代であった。
天 皇の御服も中国の服色により、冲天の位にする太陽の色である黄櫨染と定められ、文様も瑞祥の桐竹鳳とされ、平常の御服も同じ太陽の色である麦麴の麴塵の色 とされた。この麴塵は麦麴より米麴の色と変り青色系と変じて来たが、その発想は中国の理念に他ならなかった。しかしその反面日本古俗に対する関心のたかま りは、神道行事として天皇の白練絹の帛の御袍や生絹の御斎服を定められるような状態でもあった。唐風を頂点とする嵯峨天皇の弘仁期の服装は奈良の天平時代 そのままといっても過言ではない。それが徐々に国風を佩びてくるが、これは菅原道真の献言による遣唐使廃止の宇多天皇の寛平六年(894)が大きな転機と なる。これよりさき藤原氏による摂関政治は藤原良房の摂政(858)、基経の関白就任(887)によって日本式な邸宅は里内裏となり、中国式な服装に反発 を生じ、日本の板敷の家屋にふさわしい形態を求めてくることとなってくる。
和風への転換期を迎える
淳和天皇天長五年(828)をはじめとし、文徳天皇の斉衡三年(856)の袖口一尺二寸迄の禁令は事実上の袖丈の長大化の風を示すものであり、一条天皇の長保元年(999)の袖口一尺八寸以下、袴の広さ三幅以下迄の許容はその過程を如実に示しているものと云える。その間位色についても、弘仁元年(810)に二位大臣を一位と同じ深紫に、二、三位を中紫とし、やがて黒に近い滅紫、即ち黒袍となって行く。
一条天皇の長保年間(999~1004)にしばしば美服の過差、ぜいたくを禁じられているが、人々は皆新様を製して鮮美を好み今様と称したことが記されている。
従って奈良期の女装がいわゆる十二單転じて行った過程はあきらかではないが、上記の様に長保年間にはこの今様の十二單になっていたと思われる。
村上天皇の康保四年(967)に左大臣、大将となり、安和二年(969)、太宰員外師に貶せられた源高明の著になる「西宮記」には既に今日の男の束帯等の風が窺われるので、女装についても朱雀、村上両代の十世紀の中頃が唐風から和風の姿への転換の時期であり、次の冷泉、円融天皇の頃には一応その姿が整っていたのではないかと考えられる。この時代を探索することは今後の研究課題の一つでもある。
公家女房の晴れ装束
今、ここにいわゆる十二單、即ち女房の晴れの装束について述べて見る。
女房が皆具をつけた姿は物具の姿といわれ、図のいわゆる十二單にさらに比礼、裙帯をつけ、髪は結い上げ、宝冠をつけたものであった。これは奈良朝以来の古式を残す姿と云える。この物具の姿の略装としての女房直衣姿がやがて皆具の物具の姿にかわり、晴れの料として公けの場の正装として女房の晴れの装いと称されるようになってくる。
これは勿論成人女性のもので、特に着装の基本的なものが唐衣と裳でその下に袿を数枚重ねるということであった。そしてこの袿の数は三枚位から二十枚にも及んだが、大体五枚位が通常と考えられ、五つ衣の名が生まれた。したがって現在も宮中ではこの晴れの装いは「五衣、唐衣、裳」の服と呼ばれている。又、俗に十二單と称されているのは主に江戸時代の民間でのことであり、その伝承が現在にも及んでいるといえる。
しかし鎌倉時代の源平盛衰記の第四十三の二位禅尼入海の頃に建礼門院御入水の所があり、「藤重の十二單の御衣」を召されたと記されていてこの名が既にあるので、これが唐衣、裳の晴れの装いであったか重ね袿に單であったか或いは單が十二枚重ねられていたか、鶴岡八幡宮に北条政子が用いたと伝えられるものは單ばかりが組み合わされている。十二といううのはやはり古来計数の基準としての考えがあるので、極限の数という意味で多くの袷仕立の袿などを重ねるとともに、單をも用いられている非常に豪華な装いという意味と通常考えられている。
唐衣と裳をつけることは成人として晴れの姿の必須の条件であった。
又特に晴れの厳儀には下げ髪(垂髪)であっても必ず頭頂に結い上げをつくり、額、櫛、釵子をつけ、更に造花の心葉をつけることもあり、又神事には木綿鬘という白い組み糸の飾りを垂らしたりした。又既婚の人や婚約の整った人は鬢の髪の一部を切って鬢批とした。厳儀でない時は下げ髪(垂髪)のまま晴れの装いとされた。
この装いを構成するのは次の品々である。唐衣、裳、表着、打衣、袿、單、袴、更にはじめは肌に直接單をつけたが、更には小袖を下につけるのが通常となって来た。又、足に襪をはき、彩色された檜扇、即ち衵扇(後に大翳とも呼ぶ)、帖紙を持ち物としている。