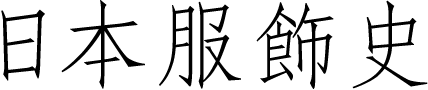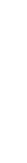菖蒲重は5月に用いました。
この色彩は葉と花の色と思われがちですが、実は葉と根元の茎の色の組み合わせです。平安時代「菖蒲の根合わせ」という、くらべっこ大会までありました。
私が重ね色目の「菖蒲」が根っこの色だったのではないかと主張するのには、もうひとつ根拠があります。「裏表の重色目」だけでなく、女子装束の「五衣の襲色目」にも「菖蒲がさね」があります。
『満佐須計装束抄』(源雅亮・平安末期)
「菖蒲、青き濃薄き・白き・紅梅濃薄き、白き生絹の単」
これはもう、色の淡い菖蒲の根の色そのままで、どう考えてもアヤメの花の色ではありませんよね。平安時代の公家たちが「菖蒲の根」に関心を持ち、その色を重ね色目に採用したことは、まず間違いないことだと私は考えております。
写真はこれもスーパーで購入した菖蒲(サトイモ科)。こちらは「紅梅濃淡」をしていますね。どうです?やはりこの重ね色目は、葉と根の色でしょう?
(有職故実研究家 八條忠基さん Facebook投稿より)