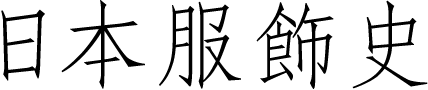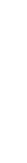孝明天皇の袞衣
袖といえば袖口の細くなった筒状のものを想像されるのではないでしょうか。
当サイトで紹介している平安時代の衣裳は袖口の大きく開いた下の方を縫い合わせない広袖のものがたくさんあります。
現在の着物は、振袖のような大きな袖でも袖口は小さく小袖です。広袖は神職の正服や僧侶の法服(袍裳)でみかけるばかりです。
いわゆる十二単に代表される広袖の衣裳は日本独自のものなのでしょうか。
広袖のルーツを探る

奈良時代から江戸時代の末まで、天皇即位の儀式で着用され続けてきた「袞衣」は唐風の衣裳です。「袞」とは首を曲げた竜のことで、中国で数種類ある冕服(袞衣・礼服)の中でも格式の高いものでした。
冕服は唐の律令を参考に日本の朝廷に導入された正装ですが冕服の制度は先秦時代にまで遡り、『礼記』にその記載が見られます。
『礼記』がまとめられた春秋戦国時代から漢代の中国は裾や袖がひらひらした深衣が主に着用されていました。(男女、階級、老若を問わず着用されたようです。後には主に女性服となりました。)
『史記』に「胡服騎射」というエピソードがあります。
紀元前326年のこと。趙の武霊王が即位したとき、国の四方は強敵に囲まれていて、常に脅威にさらされていました。当時の服装は袖も裾も長い戦闘に不向きなもので、かつ馬に引かせる戦車による戦闘を中核としていました。これは明らかに機動力・戦闘力に劣るもの。そこで武霊王は、北方の蛮族「胡」の軽快な服装と、馬にまたがって自由に戦う戦闘法を導入しようと計画しました。
中華思想が強く、遊牧民を「蛮夷」と呼んで見下し、直接馬に乗る事を蛮行と見なしていた当時では、反対する家臣も多かったのですが「胡服令」が発せられました。
胡服を広め、乗馬戦術を習得させたのです。これにより趙国は周辺諸国に連戦連勝、大いに国が栄えました。
袖の長さが決まる?
奈良時代に唐の衣服に習って筒袖だったものが、平安時代中期には広袖になっています。
しかし平安時代にどんどん袖が長くなり、これ以上長くするなと長さが定められました。

『政事要略』
「太政官符
一応定衣服制度事
右被太政官去天長五(828)年四月廿六日符称。大納言正三位兼行右近衛大将良峯朝臣安世宣。奉勅。衣袖口闊一尺二寸已下。表衣長纔着地。又衣缺腋者。自膝而上五寸為限。袴口闊又同袖口者。
斉衡三(856)年二月廿六日
左衛門大尉紀奉常奉」
装束の袖は広袖ですので、「袖口=袖丈」ということになります。これがどんどん大きく派手になってしまったので、一尺二寸(約36㎝)以下にせよ、と命じられたのです。
疫病や内裏の火災などが続き、内裏再建と社会秩序のために、長保元(999)年、さまざまな「過差停止」(奢侈禁止)令が出されました。権力者は内覧左大臣藤原道長。贅沢の極みのように描かれる人物ですが、質素倹約を奨励していました。娘の侍女が唐衣裳姿で袿を20枚重ねたりしているのに大立腹しています。
この長保元年の規制で「一尺八寸(約54㎝)以下」となっていますが、それはつまり、もっと広いのが流行していたから規制した、とも読めます。斉衡三(856)年のルールがなし崩しになっていたのでしょう。こうして規制が強化されたのですが、長保三(1001)年11月18日に内裏がまたも焼亡。規制をさらに強めて一尺六寸(約48㎝)以下、と定めました。
それにしましても、現代の装束の袖丈はとんでもなく大きいです。80㎝くらいもあり、平安当時の尺では二尺七寸ほど。現代の装束のスケールで藤原道長の絵を描くと大間違い、ということになります。
平安時代の衣裳がなぜ広袖になっていったのかは結局のところよくわかりません。
しかし広袖でだけでなく、振袖のような袂の長い袖すら東アジアを除いてほとんど見受けられません。
広袖を着る貴族の衣裳は当時でも極めて珍しいものだったのかもしれません。