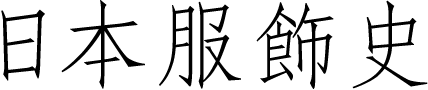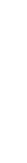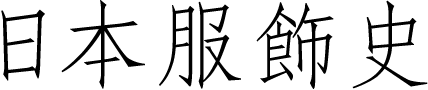
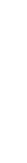
- HOME
- 衣裳の知識
- 知っておきたい御大礼
知っておきたい御大礼
用語解説
- 改元【かいげん】
元号を変えること。江戸時代以前は天皇の代替わり以外に、天変地異などの自然災害や、辛酉・甲子など特定の年(革命・革令改元)、祥瑞(主として古代)などの理由でも改元が行われたが、明治改元時に一世一元の制が定められ、天皇一代につき一年号とすることとなった。天皇が崩じた時には、速やかに年号が改められる。
- 賢所【かしこどころ】
宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のひとつで、皇祖神である天照大神を祀り、その御霊代として、三種の神器のうち八咫鏡(御代器)を奉安している。現在は、皇居内に存する。 様々な宮中祭祀が執り行われており、宮中三殿の中でも最も神聖な場所である。
- 亀卜【きぼく】
古代から宮中などで行われてきた占いの一種で、ウミガメの甲羅を焼いて、その入ったヒビの形などから吉凶等を占った。大嘗祭の神穀を供える悠紀国・主基国を決める際にも、この方法が用いられている。
- 剣璽【けんじ】
剣璽とは、宝剣と神璽のことで、瓊瓊杵尊が天照大神から授けられたとされる三種の神器(鏡・玉・剣)のうち、草薙の剣と八尺瓊勾玉のこと。皇位とともに歴代の天皇が継承してきたもので、即位の際には直ちに先帝から新天皇へ受け継がれる。
- 皇霊殿・神殿【こうれいでん・しんでん】
宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)の中で、皇霊殿は歴代天皇や皇族の御霊を、神殿は天神地祇をそれぞれ祀る。明治時代に神祇官が新たに殿舎を創建したもので、春分・秋分の日の春季皇霊祭・秋季皇霊祭などの祭祀が行われている。
- 御大礼【ごたいれい】
「大礼」とは、重要な儀式や法令などのこと。
新天皇の践せ ん祚そ から即位式、大嘗祭に至る一連の皇位継承儀礼全般のことを指す。大正天皇・昭和天皇の御大礼時には、全国各地で奉祝行事が行われ、大勢の人でにぎわった。「御大典」とも。
- 紫宸殿【ししんでん】
内裏で重要な公的行事を行う正殿。南殿ともいう。平安前期までは大極殿が正殿であったが、焼失などで次第に紫宸殿がこれに代わった。即位式や大嘗祭も紫宸殿で行われる。現在の京都御所の紫宸殿は安政二年(1855)に再建されたもの。中央には高御座が置かれる。紫宸殿の前には東に桜、西に橘が植えられ、「左近の桜」「右近の橘」と称す。
- 春興殿【しゅんこうでん】
大正天皇の即位式にあわせて、大正四年(1915)に京都御所内に造営された建物で、三種の神器のひとつの八咫鏡(御代器)を東京の皇居からこの建物に移し、賢所大前の儀が行われた。現在も京都御所内に現存する。
- 神饌【しんせん】
大嘗祭では新穀(米・粟)、白酒・黒酒、海産物の鮮物(鯛、烏賊、鮓鮑、鮭)、干物(蒸鮑、鰹、干鯛、干鯵)、御菓子(干棗、生栗、搗栗、干柿)などが神に供えられる。これらは柏の葉の容器に盛った。神饌を用意する膳屋が悠紀殿・主基殿それぞれにあり、采女らが殿舎まで行立(捧げ持って運ぶ)、殿内で神と天皇に奉る。
- 践祚【せんそ】
新天皇が先帝の崩御や譲位によって天皇位を継ぐことで、「祚」は天子の位、「践」は「ふむ」と読み、位に就くことを意味する。
奈良時代までは即位との区別はなかったが、平城天皇(五一代)が即位式以前に践祚を行ったことにより、区別されるようになったとされる。「登極令」では、「剣璽渡御 の儀」を含む一連の儀礼のことを指す。
- 即位・即位礼【そくい そくいれい】
天皇の「位」に「即」く、つまり天皇位につくこと。厳密には「践祚」とは区別されるものであるが、践祚を含む一連の皇位継承儀礼全体を指して「即位」ということもある。即位式は、新天皇が天皇位を継いだことを内外に示すもので、昭和度までは京都で行われたが、平成度は東京で行われた。
- 大饗の儀【だいきょうのぎ】
大嘗祭終了後に、天皇が参列者に白酒・黒酒などを賜う宴席にあたる儀式。皇族をはじめ、三権の長などが参加する大規模なもので、平成度には730人が招かれた。宴席は二日にわたって行われ、食後には「五節舞」や「久米舞」が披露された。
- 大嘗宮【だいじょうきゅう】
大嘗宮とは、大嘗祭が行われる建物のことで、大嘗祭のために建設され、祭儀が終了すると撤去される。中心となるのは大嘗祭が行われる悠紀殿・主基殿で、その周囲に幄舎や廻立殿などが配置される。
- 大嘗祭・大嘗会【だいじょうさい・だいじょうえ】
天皇の代替わりの年に行う新嘗祭(新米などを神に供え天皇自らも食す祭祀)のこと。
一代に一回限りで、
①神饌の新穀を悠紀田・主基田から献上する
②大嘗祭専用の建物「大嘗宮」を臨時に建てる
③祭祀終了後、節会(大饗)が開かれる
の三点が大きな特徴。大嘗宮で行われる祭祀が「大嘗祭」、節会を含む一連の行事を総称して「大嘗会」と称す。
- 高御座【たかみくら】
即位の礼の際、天皇が着座する御座のこと。
三層の壇の上に八つの柱を据え、その上に八角形の形をした屋根を配した造りで、頂上の鳳凰をはじめ鏡や玉旛で装飾され、御帳で各面が覆い、中央には御倚子が置かれる。通常は京都御所の紫宸殿に安置されているが、平成度の即位式では、皇居へ運ばれ儀式が行われた。
- 登極令【とうきょくれい】
大日本帝国憲法下で、旧皇室典範のもと天皇の代替わりに際して行われる手続きや儀式などを定めた皇室令。明治四十二年(1909)に公布され、のち附式が改正された。内容は践祚、改元、即位礼、大嘗祭など多岐に及び、附式には儀式の詳細が記される。現在は効力を有しないが、皇位継承儀礼は登極令に準じて行われるものも多い。「登極」とは、即位すること。
- 奉祝【ほうしゅく】
主に天皇や皇族の慶事、行幸などに際し、謹んで慶賀の意を表わすこと。大正・昭和の御大礼では、それ以前と異なりメディアを通して人々に広く御大礼情報が知らされた。東京・京都はもとより全国で奉祝行事が行われ、多くの記録が残された。
- 御神楽【みかぐら】
「神楽」とは、神に奉納する舞のことであるが、宮中の賢所で行われる神楽を「賢所(内侍所)御神楽」という。天岩戸の前でアメノウズメが舞を舞ったことが起源ともされ、宮中の御神楽では、神楽歌・笛・篳篥・和琴・拍子に合わせて舞う。大嘗祭などで舞われる。
- 御帳台【みちょうだい】
御帳台は、即位の礼の際、皇后が着座する御座のことで、高御座の東側に置かれる。
もとは、貴人のための座所や寝所として使われた調度であるが、「登極令」により新たに大正度の即位式から、高御座とともに皇后の御座として設けられることとなった。
- 悠紀国・主基国【ゆきこく・すきこく】
大嘗祭の際に、神穀を奉納する国郡を決定する儀式を「斎田卜定の儀」というが、そこでは、京都を中心として東・南側の「悠紀国」、西・北側の「主基国」がそれぞれ選ばれる。平安時代以降、それぞれの国は固定化したが、昭和度は悠紀が滋賀県、主基が福岡県、平成度は悠紀が秋田県、主基が大分県であった。
- 悠紀主基屛風【ゆきすきびょうぶ】
大嘗会の節会で紫宸殿の高御座の周囲に廻らす屛風。大嘗会屛風ともいう。悠紀国と主基国からそれぞれ本文御屛風(漢文の色紙を貼付、四季や瑞獣の唐絵)を四帖、和歌御屛風(和歌の色紙を貼付、卜定された国の景物や四季のやまと絵)を六帖調進した。近代の御大礼では饗宴場に、著名画家が悠紀主基地方の風景を描いた大型の屛風二双が飾られた。