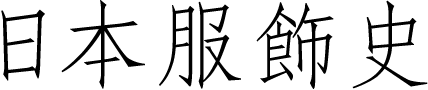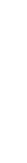湯巻は今木とも記され、本来は高貴な方が湯を使われる時、腰に巻かれるものであり、またそれに奉仕する女房達が袿か衵の上からまとったもので多くは生絹を用いていた。御湯殿での奉仕のほか天皇が理髪される時にも近侍の女房がつけている(西宮記)。また小さい御子を湯に入れる時、桶の底にもこれを敷いたことなども記されている(うつほ物語)。
この湯巻も12世紀頃には袴にかわる略装として貴族の人々にも用い出され、白平絹ではなく染付のものを着たことが平家物語にも見える。
このような風習が一般の人々にも及んでいたわけで、信貴山縁起絵巻、飛倉の巻では袿姿の長者に対して召し使いの女が小袖に文様が染められている腰布をつけている図があり、また伴大納言絵詞の町の人々の女装に染ものの腰布をつけた小袖姿がある。これは「ひだ」がないので湯巻と思われる。
また「かけ湯巻」という言葉が「とはずがたり」にあるが、このかけ湯巻というのは腰布の上端に紐がつけられていないもので、一枚の布だけのものを腰にはさんだと思われる。
ここでは薄茶色無文の帷子に縹色絁地に簡単な白纐纈文のある「かけ湯巻」をつけた姿とした。
イラストによる解説
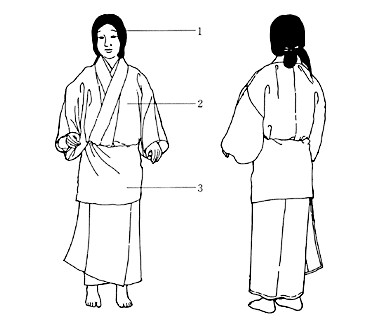
- 下げ髪
- 帷子
- かけ湯巻