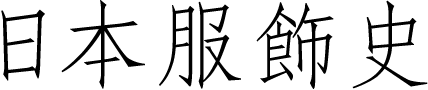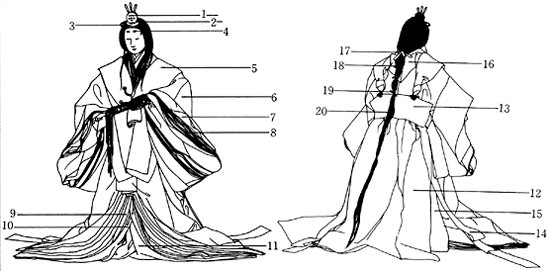平安時代中期以来の女官の晴れの装で俗にいう十二単である。応仁の大乱後、しきたりが不明となり特別の形が生まれた。即ち桃山時代前後から天保14年(1843)、平安朝の裳再興までの姿のことで、裳には唐衣と共裂の刺繡入りの懸(掛)帯が用いられ、小腰はない。引腰のあつかいは今日も完全にわかっていない。尚、この裳の下に纐纈の裳といわれる二幅の頒布のつく合計四幅の裳がつけられる。この纐纈の裳は享保7年(1722)の御再興女房装束の際廃止されている。
纐纈の裳の言葉は古いが実態の判明しているのは京都霊鑑寺に残る後水尾天皇中宮和子の遺品が最も古い。この文様は実際の纐纈でなく﨟纈で白抜きされた上に駒刺繡がなされている。またその四幅形式の伝統をうけるものが伊勢神宮の御神宝にもある。
唐衣の下は表着で、平安時代と異なり打衣は袿の下になる。袿は五つ衣と呼ばれ、五枚重ね、衽に綿を入れる。打衣の下は単である。紅の打袴に紅精好の袴を重ねてはき、扇も美しい絵文様のある檜扇(大翳、衵扇)、帖紙を持っている。髪形は下げ髪に玉かもじをつけて平額、釵子、櫛を飾る。この三種の飾りを「おしやし」とも呼んでいる。これは桃山、江戸前期の姿で、江戸後期になると髪形は鬢のはり出した「大すべらかし」となる。この図は後水尾天皇中宮和子の遺品を復原したもので、はじめて着装ここに披露するものである。重量感に溢れている。