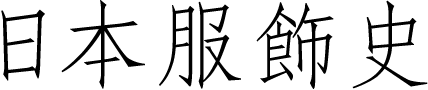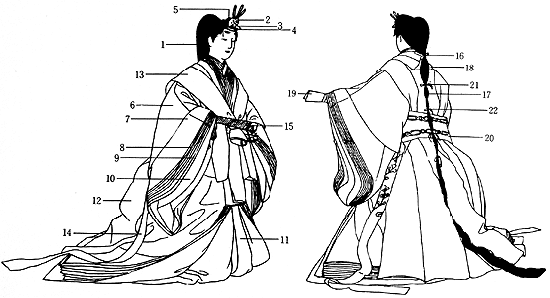平安時代中期以来の女官の晴れの正装で、俗にいう十二単である。応仁の大乱後、しきたりが不明となり特別の形が生まれ、江戸前期をへて、この姿が享保7年(1722)の御再興女房装束迄つづくが、その後、天明頃に京の町衆に流行した鬢を大きく張り出すいわゆる燈籠鬢が宮中の様式にもとり入れられて「大すべらかし」が作られるに至った、大すべらかしには玉かもじをつけて平額、釵子、櫛を飾る。この三種の飾りを「おしゃし」とも呼んでいる。裳には唐衣と共裂の刺繡入り懸(掛)帯が用いられ、小腰はない。引腰のあつかいは今日も完全にわかっていない。唐衣の下は表着で、平安時代と異なり打衣は袿の下になる。袿は五つ衣と呼ばれ、五枚重ね、裾や衽に綿を入れる。打衣の下は単である。紅の袴をはき、扇も美しい絵文様のある檜扇(衵扇・大翳)、帖紙を持っている。ここに示すのは天明頃から天保14年(1843)平安朝の裳再興迄の姿とした。
江戸後期・正装の公家女房
Court lady in formal dress.