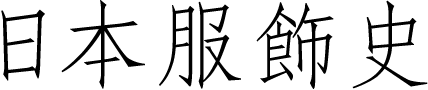日本の甲冑の歴史を古代から幕末の終焉まで時代を追って解説していきます。
古代の甲冑 ~短甲・挂甲~
日本における甲冑の歴史は実に古いものです。
古くは弥生時代の遺跡から短甲(木製)の部分とおぼしきものが発掘されています。

古墳時代に入ると、金属が使用されるようになり、短甲にも金属製のものが見つかっています。また、古墳時代の甲冑の様子を窺い知ることができるものとして、古墳から出土した埴輪で武装した姿のものが見つかっています。
短甲とは、胴を守る丈の短い甲のことで、「みじかよろい」とも呼ばれます。
金属製の短甲は鉄板同士を接続する鋲留めの技法や、覆輪の技法が用いられています。
この時代の短甲には、腰回りの防御である草摺、肩から二の腕を守る肩鎧(後世の袖に当たる)、腕を守る籠手、脚を守る脛当などを揃えるようになり、おおよそ後世で甲冑武装する時の部分が完備し始めています。
また、同じく古墳時代の遺跡で見られる甲冑に、挂甲というものがあります。
挂甲とは、革や鉄の小札を韋か紐で綴じて一枚の板とし、この板を繋いで構成した甲冑です。この挂甲には二つの形式があり、一つは胴全体を巻いて体の前で引き合わせる「胴丸式挂甲」、もう一つは貫頭衣のように胴の前後の部分を作り、両脇を塞いだ「裲襠式挂甲」です。
挂甲は首長などの支配者が着用しました。堅固で体に馴染みにくい短甲に比べて、挂甲は体を自由に曲げ伸ばしできる利点があり、奈良時代には高級武人用として用いられました。
これらの甲冑は、札の綴じ方や威し方など、後世の甲冑を構成する手法に繋がっていきます。特に「胴丸式挂甲」は、平安時代末期頃に完成し重用された胴丸の形へと繋がっていきます。

一方、「裲襠式挂甲」は、伝統を重んじる朝廷の武官の武装に用いられるようになり、やがて形式化していきました。近代に見られる天皇即位の御大典では、近衛の次将が武官の闕腋袍の上に着用している裲襠に、その形式が受け継がれています。
一般兵士は軽くて安価な綿襖甲(綿襖冑)を用いました。挂甲は大量の鉄片を用い、製作に手数がかかり大量生産するのは難しいためです。綿襖甲は唐風の甲冑で、コート状の布に革または鉄の小さな板を綴じ付けたもので、防寒にも優れていました。
短甲と挂甲は奈良時代を経て、平安時代の初期頃まで用いられていたことが『延喜式』から窺えます。その過程で見られた大きな変化は、甲冑の素材です。
古墳時代から続く短甲・挂甲は金属製、鉄の板によって作られていました。鉄の板による甲冑は確かに堅牢ですが、その分重量があり行動に不便でした。また、綴る絲や韋が損傷しやすいという欠点がありました。そのため、奈良時代終末期の光仁天皇(在位:770~781)や平安時代初頭の桓武天皇(在位:781~806)の二度にわたり、鉄鎧は不便なので革製の甲冑に切り換えるよう命令が出されました。
革は加工によっては鉄に準じて堅牢であり、軽いのです。しかし有機質である分、長い年月が経つと脆くなり、漆加工が未熟で風化しやすいものでした。
この時代の短甲・挂甲・綿襖甲はその材質のためや、度重なる戦乱で失われた結果、ほとんど現存していません。ですが、この頃の甲冑の様式は、やがて台頭した武家階級が経験により改良した大鎧や胴丸へと引き継がれていきます。
平安時代 大鎧・胴丸の成立

武家階級が台頭した平安時代の末期頃、短甲や挂甲の形式に改良を重ねた大鎧や胴丸が成立します。これは日本の甲冑の歴史における大きな転換期でした。
大鎧は騎馬戦が主流であった平安時代末期の戦い方に適した鎧でした。馬上で腰から大腿部にかけて四方を取り囲むように草摺で覆う四間草摺、弦走韋、栴檀板と鳩尾板などが大鎧の大きな特徴です。その特徴の詳細については「式正の鎧・大鎧」のページを参照ください。
胴丸は軽武装用や徒歩武者用に適したものとして生まれました。奈良時代まで使用されていた「胴丸式挂甲」から発展して成立したものと思われます。挂甲の場合は胴の引合せが前中央でしたが、胴丸の場合は引合せが右脇になっています。また、草摺の数は初期こそ大鎧と同じ四間草摺でしたが、時代を経るごとに分割し、最終的に八間草摺に変化していきました。これは徒歩武者向きに足捌きを良くするためです。

胴丸を着用した徒歩武者は、元々は兜・袖・籠手・脛当を用いない軽武装でした。しかし、大鎧と比べて着用が簡単な胴丸を、やがて上級の者も着用するようになり、その場合は大鎧と同様に、兜・袖・籠手・脛当をつけるようになりました。
胴丸は軽武装用や徒歩武者用に適したものとして生まれました。奈良時代まで使用されていた「胴丸式挂甲」から発展して成立したものと思われます。挂甲の場合は胴の引合せが前中央でしたが、胴丸の場合は引合せが右脇になっています。また、草摺の数は初期こそ大鎧と同じ四間草摺でしたが、時代を経るごとに分割し、最終的に八間草摺に変化していきました。これは徒歩武者向きに足捌きを良くするためです。
胴丸を着用した徒歩武者は、元々は兜・袖・籠手・脛当を用いない軽武装でした。しかし、大鎧と比べて着用が簡単な胴丸を、やがて上級の者も着用するようになり、その場合は大鎧と同様に、兜・袖・籠手・脛当をつけるようになりました。
鎌倉時代 実戦を通して改良される大鎧・胴丸 そして腹巻
大鎧や胴丸が成立した平安時代には騎射戦が主でしたが、鎌倉時代に入ると戦闘法が変化していきました。
騎射戦は相変わらず行われていましたが、戦闘規模が拡大し、下級の徒歩武者が増えたことにより、甲冑に求められる要素もまた変化しました。

大鎧は元々馬上での戦いに適した甲冑でしたが、馬上で相手と斬り合ったり、組み打ちしたり馬を射て敵を落馬させる戦闘法が広まるにつれて、従来の大鎧よりも動きやすいものが求められるようになりました。
そのために求められたのが、〝腰で着る〟甲冑です。機敏に動くためには、腰で鎧の重さを支え、両肩にかかる鎧の重さを軽減する必要がありました。そのために、胴の幅が従来の裾広がりから上下同幅、もしくはやや裾すぼまりへと形状が変化し、腰に密着するようになりました。また、平安時代のものと比べて、胴の丈が短く変化するなど、腰で鎧の重量を支える工夫がなされました。
時代が下り鎌倉時代後期の頃になると、より便利な胴丸が主流になり、大鎧は象徴性が強まりました。
美術工芸的にも優れた大鎧は武家の社会的シンボルとして、きらびやかな金銅の飾りが用いられ、彫金物の装飾が多用されるようになりました。
また、韋所の文様にも変化が見られました。平安時代には襷に霰と獅子丸の模様などが主に用いられていましたが、鎌倉時代になると、獅子牡丹文や牡丹を背景にした不動明王二童子像が多く使われるようになりました。
胴丸は、下級の徒歩武者が増えたことによって、より実戦に適した形へと進化していきました。大鎧よりも動きやすい胴丸は、やがて兜・袖・脛当などをつけて大鎧に代わり上級の武者にも用いられるようになりました。

腹当・腹巻
腹当とは、最も簡略化された甲冑です。胴の前部だけを防御する腹当に、その両側をさらに一間分ずつ増したのが腹巻です。
この形状だと背中の隙間が多いのですが、武士は敵を前面に受けるのが面目であるため、敵に背を見せることを潔しとしませんでした。そのため、背中の隙間はさほど意識せずに用いられました。
腹巻もまた胴丸と同様に徒歩戦で動きやすい甲冑のため、やがて主流となっていきました。
(※平安時代から鎌倉時代までの鎧の変化については「式正の鎧・大鎧」のページを参照)
南北朝時代から室町時代にかけて
南北朝時代は、朝廷が北朝・南朝に分かれ、争いの絶えない時代でした。
この頃の戦闘は騎馬戦から徐々に徒歩戦に移行していき、この変化に伴い騎馬戦に適した大鎧は実戦において不便になり、やがて権威の象徴的存在となっていきました。
一方、実戦で主流となったのが胴丸や腹巻です。
胴丸は兜・袖・籠手・脛当をつけた重武装となり、腹巻は背中の引合せ部分の隙間を防御するための背板(臆病板)をつけるようになりました。また小札の長さが短くなり、この時代の甲冑は従来のものと比べて胴の丈が10㎝ほど短くなりました。
またこの頃の変化として、威し方の簡素化が挙げられます。平安時代以降、小札を横へ威していく毛引威が伝統的に行われてきましたが、南北朝時代に入ると、間隔を粗くして所々に縦に二筋ずつ並べる素懸威という簡易な威し方が始まり、室町時代末期からは素懸威が従来の毛引威と並んで一般的な威し方となりました。
そのほか、小札にも変化が表れました。従来のような小札と異なり、札を半分ずつ重ねるのではなく、札の四分の一程度を合わせる伊予札が用いられるようになりました。さらに時代が下って室町時代末期頃になると、たくさんの小札を横一列に綴じて一段を作る代わりに、一枚の板で一段とする板札が多く用いられるようになりました。
威し方を簡略化した素懸威と板札の利用は、それまでの甲冑製作と比べて大幅なコストダウンと量産化を可能にしました。
また、南北朝時代から室町時代前期頃にかけて、腹巻を中心に(一部胴丸でも)韋包の技法が行われました。韋包とは、胴の表面を綾や熏韋で覆い隠す技法です。傷んだ小札を集めて綴じ付けても形が崩れないようにするもので、戦闘で壊れた甲冑を再利用する工夫でした。
戦国時代 当世具足
日本の甲冑の歴史において、戦国時代は平安時代末期の大鎧・胴丸の完成に次ぐ大きな転換期でした。

戦国時代に入ると、槍・弓を始めとして、新しい兵器である鉄砲が活用されるようになり、これらの武器を用いた戦闘に対応した部隊と、より頑丈で軽快な動きができる甲冑が必要とされるようになりました。
この時代に成立したのが当世具足です。「当世」とは現代風という意味で、「具足」とはすべて備わっていることを表します。当世具足は防御機能が完備した現代風の鎧という意味で名付けられました。
当世具足は胴丸の系統から発展して生まれました。胴丸と異なるのは、前立挙三段、後立挙四段、長側五段と、各段とも胴丸よりも一段ずつ多いところです。各段を構成する札には、従来の小札のほかに、室町時代末期頃から登場した板札が使われました。板札は小札を威すよりも製作が遙かに簡単である上に、槍や鉄砲に対して防御力が高かったのです。
この時代の甲冑には鉄を多用するようになり、板札も鉄を使ったものが多くなりました。その方が堅牢ですが、何枚もの小札を威して作った胴と比べて伸縮しないので、そのままでは着脱できません。そのため、胴全体を縦方向に2~6枚の部分に分けて、蝶番をつけてつなぎ、開閉できるようにしました。また、鉄の板札でできた胴は鋲留されているため伸縮しないので、腰骨に当たって痛めないように左右の脇が切り上げられています。
胴と草摺をつなぐ揺絲は、従来の大鎧・胴丸・腹巻などに比べて長くなっています。これは打刀を差すための紐を揺絲の上から胴に巻いても草摺が自由に動くための工夫です。
肩に当たる肩上部分は、背中部分の押付板と綴じ付けますが、ここに襟板をつけ、首を守る襟廻しと、肩を守る小鰭がつきます。
また、背中には差物(戦場で個人や部隊を識別するための目印など)をつけるための合当理という装置がつくようになりました。
南蛮胴具足 ~西欧甲冑の影響~
戦国時代にはスペイン・ポルトガルとの交易(南蛮貿易)が行われ、西欧の甲冑が日本に輸入されました。この甲冑に一部手を加えて流用したのが南蛮胴具足です。南蛮胴の遺物としては、徳川家康所用のものが有名です。
主な南蛮胴の特徴
- 前後の胴が各一枚の鉄板で作られていること。
- 正面の胸から腹にかけて盛り上がり鎬があること。
- 発手(胴の下端)がV字になっていること。
- 胴の腕の部分などは、日本の甲冑で用いる覆輪を用いず、直接ひねり返して縄目状の文様がつくように叩いて補強していること。
南蛮胴は鉄砲の攻撃に対して有効でしたが、金属製のため重量があり、また高価なものでした。そこで南蛮胴を真似て日本人の体型に合う胴が作られるようになりました。日本で作られた南蛮胴は元来の南蛮胴と異なり、発手がV字ではなく、日本の甲冑と同じく平らです。
個性的な甲冑が生まれたのもこの時代です。
それまでの甲冑は、威毛の色や威し方によって美意識を主張していました。しかし当世具足では、本小札・伊予札・板札を使い分け、胴の構成も様々なものを用い、個性を主張しました。
朱漆塗の甲冑が普及したのもこの頃です。朱漆の顔料は辰砂(水銀と硫黄の化合物)やベンガラ(酸化鉄)を用いるため高価でしたが、室町時代末期から安土桃山時代にかけて、中国から大量の辰砂が輸入され、甲冑にも朱漆を使えるようになりました。朱漆の甲冑として有名なのは「井伊の赤備え」です。
江戸時代 ~太平の世 復古調の鎧~
江戸時代に入ると、島原の乱(1637)以降、平和な時代が200年以上続き、武士が甲冑を着て活躍するような機会はなくなりました。そのため、甲冑は具足櫃に納められたままとなりました。
各藩にはお抱えの甲冑師がいました。有名なのは明珍派と名乗る一派です。明珍派が得意としたのは鉄の鍛えと加工技術でした。やがて鍛えの良さを競うようになり、江戸時代中期頃になると、着用における実用性よりも、鍛鉄技術や工芸的技術の向上に重きを置くようになっていきました。
この時代、軍学者が考案した甲冑の改良もあります。代表的なものとして瑠璃斎胴の発明があり、懐中のものを出し入れする時に便利なように胸板から立挙の一部が蝶番付きになっています。
戦のない平和な時代であった江戸時代では、甲冑は実用性よりも、飾った場合の立派さが重視されるようになりました。そのため、実用には不便な防具を、立派に見えるからという理由でつけたり、不必要な部品をつけたりしています。また、江戸時代中期以降になると、当世具足以前の大鎧や胴丸・腹巻に関心が持たれるようになり、甲冑の復古調の時代となりました。
大鎧・胴丸・腹巻を再び作るようになったものの、当世具足の手法が抜けきれず、また古式甲冑の研究が不充分なままであったので、それぞれの甲冑を特徴付ける決まり事が破られた結果、異様な甲冑が生まれました。
一方、各藩で独自の具足が受け継がれるという例もありました。著名なのは仙台藩伊達家に伝わる重厚な造りの雪の下胴具足、細川家の身動きしやすい簡素な越中具足、前田家の高度な工芸技術を施した加賀具足などです。
幕末 甲冑の終焉
19世紀後半の幕末、長州藩と薩摩藩を中心に倒幕運動が起こり、再び戦乱の時代となりました。
この時代の武器の主流はかつての槍や弓、鉄砲ではなく、近代的な洋式銃や大砲などに移り、近代の戦闘法に対応できなかった甲冑は幕府の終焉とともにその役割を終えたのです。